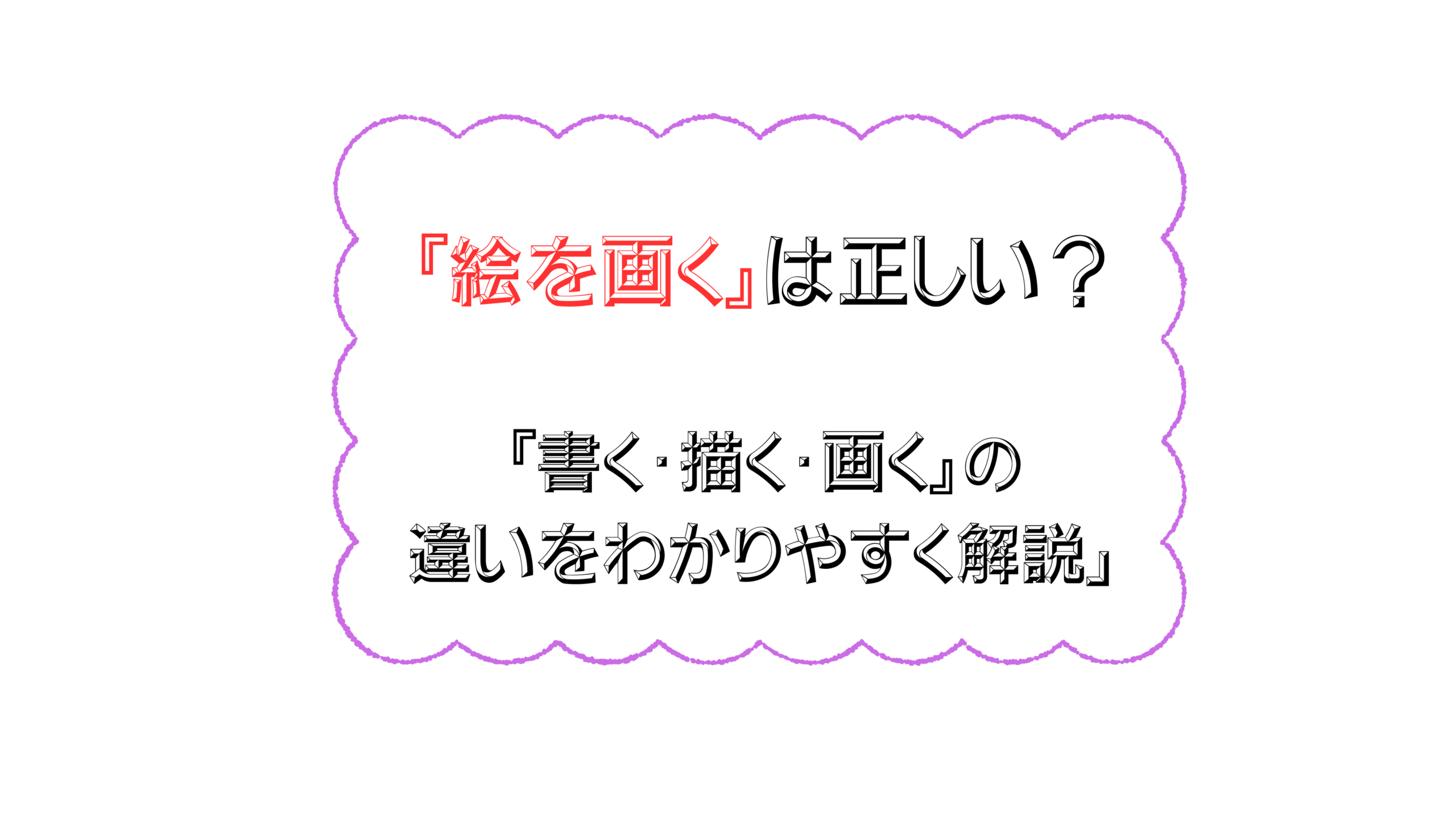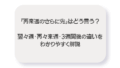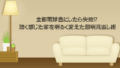「絵を画く」「絵を描く」「文字を書く」──どれも「かく」と読みますが、使い分けに迷うことはありませんか?
同じ読みでも、実は意味や使う場面が少しずつ異なります。
この記事では、「書く」「描く」「画く」という3つの漢字の違いを、語源・意味・使われ方の観点からわかりやすく整理します。また、「絵を画く」という表現が正しいのか、現代日本語や辞書の記述に基づいて丁寧に解説します。子どもや学習者にも説明しやすいよう、実例や語感の違いも紹介します。
「書く・描く・画く」3つの違いをざっくり比較

「かく」という言葉は、同音異義語の代表格です。日本語では一つの読みでも複数の漢字があり、それぞれ意味や使い方が違います。
| 漢字 | 意味 | 主な使い方 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 書く | 文字や文章を記す | ノートに書く・手紙を書く | 「日記を書く」 |
| 描く | 絵やイメージを表す | 絵を描く・夢を描く | 「未来を描く」 |
| 画く | 図形・設計・構想を表す | 設計図を画く・計画を画く | 「理想の都市を画く」 |
3つに共通するのは「形を作る」という点です。しかし、対象物が「文字」「イメージ」「構造」なのかによって、使う漢字が変わります。
「書く」の意味と使い方──文字や記録を残すときに使う言葉
「書く」は最も日常的に使われる「かく」です。手紙、メモ、文章など、文字や記号を紙や画面に記す行為を表します。日本語の中でもっとも基本的な動詞の一つであり、古代から使われてきました。
主な使い方
- 手紙・日記・メモを書く
- 文章・原稿・レポートを書く
- 名前を書く・署名を書く
例文
- 「手帳に予定を書き込む」
- 「小説を書いている」
- 「黒板に文字を書く」
この「書く」は、情報を記録する行為に焦点を当てます。頭の中にある言葉を外に出し、他人に伝える、あるいは自分のために記録するという意味合いです。
関連語・類義語
- 記す(しるす):少しフォーマル。「記録する」に近い。公文書や報告書などで使われます。
- 綴る(つづる):言葉や文章を丁寧につなぐ意味。創作や詩的な場面で使われます。
- 筆を取る:文学的な表現で、物語や詩などを書くときに使われます。
「書く」は誰もが日常的に行う動作であり、学びの基本でもあります。日本語教育では最初に教えられる漢字のひとつでもあります。
「描く」の意味と使い方──イメージを形にする表現
「描く」は、目に見える形や心の中のイメージを表すときに使います。「絵を描く」はもちろん、「夢を描く」「理想を描く」といった抽象的な使い方もできます。
主な使い方
- 絵やイラストを描く
- 夢・理想・希望を描く
- 頭の中でイメージを描く
例文
- 「風景をスケッチブックに描く」
- 「子どもの将来像を描く」
- 「優しい世界を心に描く」
「描く」は、単に線を引くというよりも、“思いを形にする”というニュアンスがあります。感情や想像力を外に出す行為であり、芸術的・創造的な場面で多用されます。
関連表現
- 表す:感情や考えを外に出す。例:「喜びを表す」
- 想像する:形のないものを心の中で思い浮かべる。
- 表現する:言葉や絵、音楽などで他人に伝える。
「描く」は“見えないものを見える形にする”動詞と言えるでしょう。
「画く」の意味と用法──設計や構想を表す言葉
「画く(えがく/かく)」は、線を引いて形を作る、または計画を立てるときに使われる漢字です。日常会話ではやや硬い印象を与えますが、建築・デザイン・都市計画など専門的分野では今も頻繁に使われます。
主な使い方
- 設計図を画く
- 計画・構想を画く
- 地図を画く
例文
- 「新しい都市計画を画く」
- 「建築士が設計図を画く」
- 「理想の未来を画く」
「画く」は、“正確さ”や“構造的な思考”を表す言葉です。単なる描写ではなく、全体の構成や仕組みを頭の中で設計し、線で表す行為に重点があります。そのため、「画策する」「画定する」といった派生語でも使われます。
関連語
- 設計する:構造や計画を細かく立てる。
- 構成する:全体を組み立てる。
- 企画する:計画を立て、実現を目指す。
このように「画く」は、芸術よりも構造・思考の分野で生きている言葉です。
「書く」「描く」「画く」の使い分けポイント

| 対象 | 適切な表現 | 例文 |
|---|---|---|
| 文章 | 書く | 文章を書く |
| 手紙 | 書く | 手紙を書く |
| 夢 | 描く | 夢を描く |
| 絵 | 描く | 絵を描く |
| 設計図 | 画く | 設計図を画く |
| 計画 | 画く | 計画を画く |
| 心の中の未来 | 描く | 心の中で未来を描く |
👉 ポイント:対象が「文字」なら書く、イメージや感情なら描く、構造や計画なら画くが自然です。
豆知識:「絵を画く」は正しい?──辞書的な解釈と実際の使われ方

「絵を画く」という表現は、間違いではありませんが、一般的ではありません。現代日本語では「絵を描く」が自然で、教育現場でも「描く」を用いるのが標準です。
ただし、「画く」には「線を引いて構図を作る」という意味があるため、絵の制作工程や芸術的な構図設計の文脈では使われることもあります。
例文で比較
- 「設計者が未来都市を画く」 → 正しい・専門的な表現
- 「子どもが絵を画く」 → 文法的には可能だが、硬い印象
つまり、「絵を画く」は文学的・芸術的な表現としては成立しますが、日常では「絵を描く」が自然です。
子どもに説明するときのコツ
子どもや学習者にこの違いを教えるときは、難しい説明よりも実際に体験させるのが効果的です。
説明例
- 「書くは、文字を書くときに使うよ」
- 「描くは、絵や夢をえがくときに使うよ」
- 「画くは、設計図や地図をつくるときに使うよ」
実際にノートやスケッチブックを使い、3つの“かく”を行動で見せると理解が早まります。教育の場では「動作と意味の一致」が大切です。
よくある質問(Q&A)

Q1:「絵を画く」と「絵を描く」はどっちが正しい?
A:一般的には「絵を描く」が自然です。「画く」は建築や設計など専門分野で使われることが多いですが、文学的な文章で意図的に使うケースもあります。
Q2:「描く」と「表す」はどう違うの?
A:「描く」はイメージを形にすること。「表す」は気持ちや考えを外に出すこと。たとえば、「夢を描く」は心の中で思い浮かべるニュアンス、「気持ちを表す」は行動や言葉で伝えるニュアンスです。
Q3:「画く」はどんな場面で使えばいいの?
A:図面や設計、国家構想など“線や形を意識する場面”で使います。「設計図を画く」「国家の未来を画く」などが代表例です。
Q4:辞書ではどう定義されているの?
A:辞書によると、
- 書く:文字や記号を記すこと。
- 描く:線や色で形やイメージを表すこと。
- 画く:線を引いて図形・設計を作ること。
いずれも“形をつくる”点で共通しています。
日本語学的な補足:語源と変遷
「書く」は古代日本語の「カク(掻く)」がもとで、もともとは“線を刻む”という意味を持っていました。その後、筆や墨の文化が広まるにつれ、“文字を記す”意味に転じました。
「描く」は、中国語の「描(ミャオ)」がもとで、絵や模様を線で表すという意味から日本に伝わりました。「画く」も中国由来で、線を引く・図を作ることを意味します。
つまり、3つの漢字は歴史的にも関連があり、古くは「書く=線を刻む」「描く=線で形を作る」「画く=線で設計する」という共通ルーツがあります。
まとめ:「書く・描く・画く」を使い分けて日本語をもっと楽しもう

| 漢字 | 主な意味 | 用例 |
|---|---|---|
| 書く | 文字や文章を記す | 「手紙を書く」 |
| 描く | イメージや感情を表す | 「夢を描く」 |
| 画く | 構図や計画を作る | 「設計図を画く」 |
日本語は同じ音でも、漢字の違いで表現の幅が大きく広がります。「書く・描く・画く」を正しく使い分けると、文章に奥行きと表現力が生まれます。ぜひ、日常の中でも意識して使ってみてください。
📝 免責・出典
※本記事は日本語表現に関する一般的な情報提供です。正確な用法については、国語辞典(広辞苑・大辞林など)や公的資料をご参照ください。