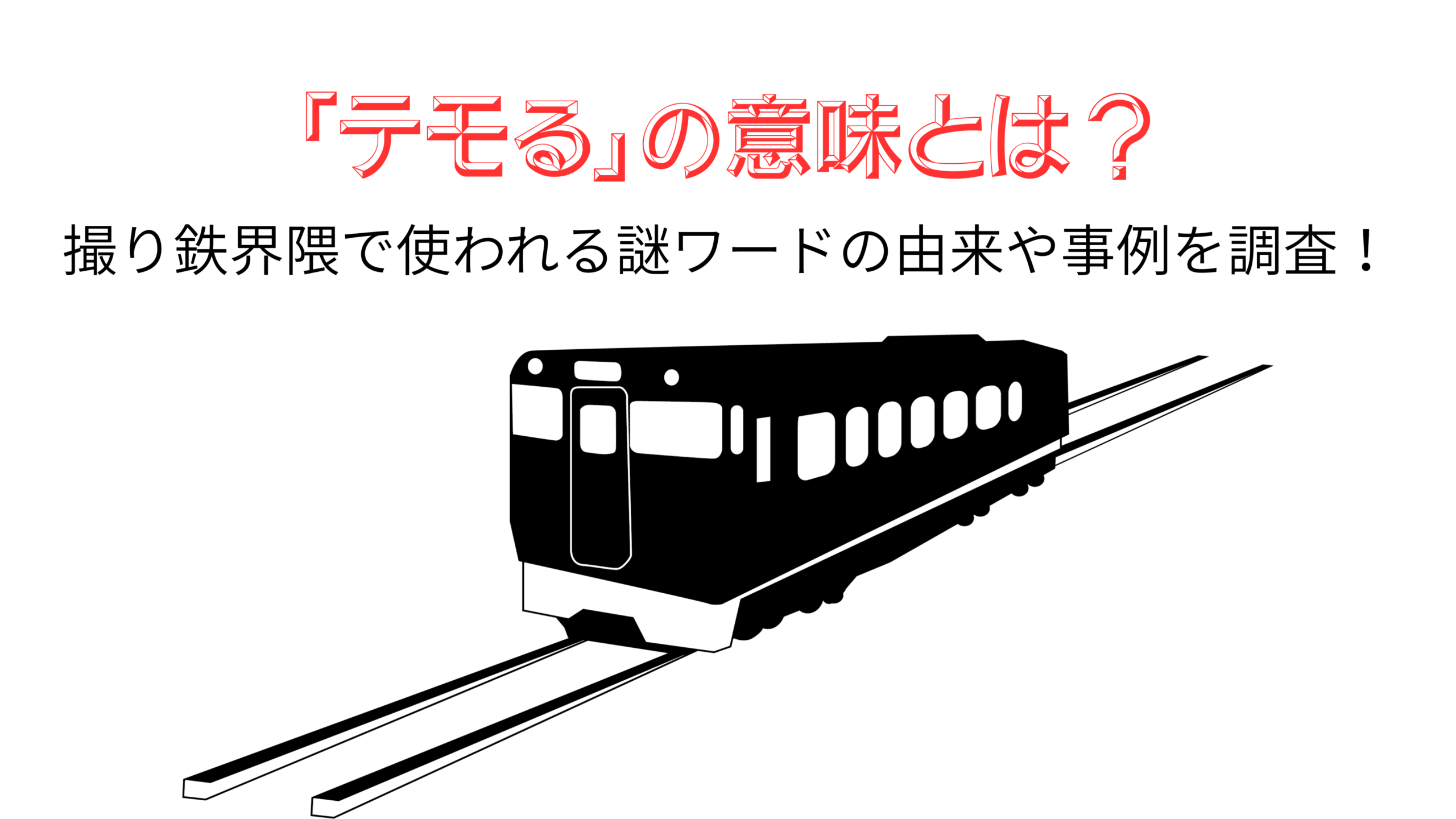電車好きの方たちが使う言葉の中には、初めて耳にすると「えっ、それどういう意味なの?」と戸惑ってしまうような、不思議で独特な表現がたくさんありますよね。特に、鉄道ファンの間では日常的に使われているものの、一般の方にはなじみのない専門用語やネットスラングが多く存在しています。
今回注目したのは、SNSなどで最近とくによく見かける「テモる」という謎のワード。ひと目見ただけでは想像もつかないその意味や使われ方が、ちょっと気になりますよね。
このブログでは、「テモる」という言葉がどういった場面で使われているのか、実際の投稿例やその文脈を通してご紹介します。また、撮り鉄さんたちの間でどのような意味をもって使われているのか、その背景やネット上での広まり方についてもやさしく解説していきます。
鉄道ファンの世界に詳しくない方でも、読みながら「へぇ、そんな文化があるんだ」と興味を持ってもらえるように、わかりやすく丁寧にご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね♪
話題になった「テモる」投稿の背景とは
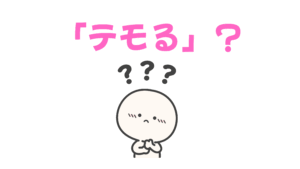
SNSなどで注目を集めた投稿に、次のような一文がありました。
「神立試単が北千住でテモりました」
この投稿を見て、「テモるってどういう意味?」「神立試単って何のこと?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
まず、「神立試単」というのは、茨城県にある神立駅から出発する試運転列車を示しており、「試単」は“試運転列車の単独運行”を略したものです。鉄道ファンの間ではよく使われる略語のひとつですが、一般的にはなじみのない言葉ですよね。
そして、この文中にある「テモる」という言葉が今回の主役です。投稿の中では、「テモる」が“何か想定外のトラブルが起きた”ような雰囲気で使われていますが、具体的に何が起きたのかは書かれていません。ただ、その曖昧さゆえに「何か非常事態が発生したのでは?」「列車が停まってしまったのでは?」と、SNS上で大きな話題となったのです。
この一文は、鉄道ファン同士の情報共有として投稿されたものでありながら、言葉の珍しさやインパクトから、ファン以外のユーザーの注目も集めたことで、一気に拡散されていきました。
こうした投稿をきっかけに、撮り鉄文化や鉄道界隈特有の用語に関心を持つ人が増えているのも興味深いですね。
「テモる」の意味を考察

「テモる」はどういう状況で使われている?
「テモる」という言葉は、最近SNSを中心に鉄道ファンの間で使われるようになった独特な表現です。
その意味合いとしては、電車が本来の運行スケジュールどおりに進まなくなったとき、特に“予定外の理由”で止まってしまったような状況を指して使われることが多いようです。
なかでも、撮り鉄さんたちの撮影行動が原因で駅が混雑したり、安全確保のために運転を一時見合わせたりするような事態が起きた場合に、「テモった」と表現されるケースが見られます。
「テモる」という響きは、どこか軽いノリを感じさせつつも、その背景にはちょっとしたトラブルや、マナー違反の可能性が含まれている場合もあります。あえて直接的に「迷惑行為」と言わず、“やんわりオブラートに包んで表現する”言葉として使われているのかもしれません。
また、人によっては「事故」「混乱」「緊急停止」などの深刻な言葉を避けるための、ネットスラングとして自然に使い始めたという見方もあります。たとえば、「今日は〇〇駅でテモってたらしいよ〜」といった軽い会話の中で登場することも多く、ファンの間では通じる言葉として定着しつつあるようです。
このように、「テモる」は一見なんとなく使われていそうな言葉ですが、その背景を探っていくと、鉄道とファンの関係性やマナー意識、SNS文化の影響などが垣間見える、非常に興味深いワードなのです。
緊急停車やファンの殺到に使われるケース
・武蔵野線での緊急停車
ある日、武蔵野線の電車が突然停止したという報告がSNSで話題になりました。詳細な原因までは明らかになっていないものの、その際に「またテモった?」という反応が多く寄せられていたことからも、鉄道ファンのあいだではこの言葉がある種の“定番表現”として使われていることがうかがえます。列車が予期せぬタイミングで止まるという出来事は、日常的ではない分、インパクトが大きく、印象に残りやすいですよね。
・機関車ラストランでの混雑
鉄道ファンにとって特別なイベントである「ラストラン」。人気のある機関車が最後の運行を迎える日には、多くのファンが集まり、写真や動画を収めようと熱気が高まります。その結果、駅構内が異常な混雑状態になってしまい、安全面の確保が難しくなったり、列車の運行にまで影響が出てしまう場合もあります。そういった状況の中で、「今日のラストランはテモったらしい」といった表現がSNSで見られるようになります。
こうした事例を見てみると、「テモる」という言葉は単なるトラブルの発生というよりも、鉄道ファンの集まりや行動によって、結果的に列車の運行が一時的にストップしたり乱れたりした際に使われるようです。そのため、少しだけ皮肉を込めて、そしてある種“笑い話”のように使われているのかもしれません。
「テモる」という表現には、鉄道ファン自身が自分たちの行動を俯瞰して見たり、自虐的に語ったりするようなニュアンスも含まれている印象を受けます。とはいえ、トラブルが起こってしまうと多くの人に迷惑がかかるため、やはりマナーを守って楽しむ姿勢が大切ですね。
「テモる」は撮り鉄界隈のネットスラング?
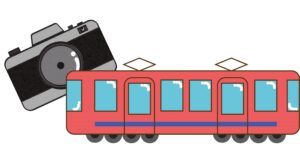
この「テモる」という言葉、実はまだまだ一般的には知られていないものの、鉄道ファンのあいだではじわじわと浸透してきているネットスラングのひとつです。
辞書に載っているような正式な日本語ではないため、学校や職場などの日常会話では聞き慣れない言葉かもしれませんね。そのため、「テモるって何?」「どういう意味?」と気になる方も多いはずです。
「テモる」という表現は、おそらく“ネット上で自然発生的に生まれた造語”であり、とくに撮り鉄さんたちの間で使われ始めたことがきっかけで広まったと考えられています。
語源については諸説あります。たとえば、「手持ち撮影(てもちさつえい)」や「手元ブレ」といった、カメラに関する言葉が省略された結果「テモる」になったのでは?という説もあります。また、ある鉄道イベントでファンの行動が原因で運行トラブルが発生したことを皮肉って、その出来事が「テモった」と表現されるようになった…という話も聞かれます。
ただし、どの説もはっきりとした裏付けがあるわけではなく、あくまでネット上の推測や噂レベルの話として語られているのが現状です。それでも、その響きの面白さや独特さから、多くのファンに親しまれるようになり、今では撮り鉄界隈では比較的よく知られている言葉のひとつになってきています。
中には、「またテモったの?(笑)」といった感じで、ちょっとしたジョークやアイキャッチ的に使われる場面も増えており、単なるスラングにとどまらず、コミュニティ内での共通認識として定着しつつあるように感じます。
過去にもあった!電車が止まった撮り鉄騒動
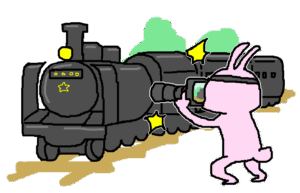
「テモる」という言葉こそ使われていなかったものの、それに近いような騒動やトラブルは、過去にも何度も起きています。
たとえば、撮影に夢中になるあまり、以下のような行動が問題視されたケースも。
・鉄道写真を撮るために立入禁止エリアである線路に入り込んでしまい、列車が緊急停止。運行ダイヤに遅れが生じ、乗客の予定にも大きな影響を与えました。
・駅のホームで大型の三脚を設置し、それが通行の妨げとなってしまったため、駅員さんが対応に追われたというケースもありました。
・撮影の際、ホームの端ギリギリに立って他の乗客が不安を感じたという声や、撮影中に注意を無視してしまった結果、駅員や警察が出動した事例も報告されています。
こうした一部のマナー違反が原因で、撮り鉄全体のイメージが悪化してしまうこともあります。
鉄道ファンにとって、思い出に残る一枚を撮ることは大きな楽しみのひとつですが、そのためには周囲の安全やマナーを守ることが前提です。
「鉄道が好き」という気持ちはとても素敵なもの。その気持ちを守り続けていくためにも、一人ひとりがルールを守って楽しむ姿勢を大切にしたいですね。
撮る側も、利用する側も、そして運営する側も、すべての人が気持ちよく鉄道を楽しめる環境づくりがこれからもっと求められていくのではないでしょうか。
撮り鉄・鉄道ファンが使う独特な専門用語一覧

せっかくなので、他にもよく使われている撮り鉄用語をいくつかご紹介します♪
- バルブ:シャッターを長時間開けて撮る夜景写真のテクニックです。夜の駅や走行中の列車のヘッドライトを幻想的に写したいときなどに使われ、三脚やリモートシャッターが必須になることもあります。光の線が流れるように映るため、芸術的な写真が撮れるとして人気の高い手法です。
- 被り(かぶり):撮りたい電車の前に、通過中の別の電車や人が写り込んでしまい、写真が思い通りに撮れなかったときに使われる言葉です。特にシャッターチャンスを狙っているときに発生すると悔しさが倍増。「今日は〇〇で被った…」とSNSで報告されることも。
- 串パン:パンタグラフ(電車の屋根についている電気を取る装置)が複数写ってしまい、車両の屋根部分がゴチャゴチャに見えてしまう状態です。「串に刺さったパンタグラフのように見える」ことから名付けられました。写真としての美しさが損なわれるため、避けたい現象とされています。
- 順光(じゅんこう)/逆光(ぎゃっこう):太陽の位置によって写真の仕上がりが大きく変わるため、撮影前に意識される言葉です。順光は車両の側面にしっかり日が当たる状態で、色がくっきりと出ます。一方、逆光は逆に影になりやすく、場合によってはシルエット風になることもあります。
- 同業者:現場に集まった他の撮り鉄さんたちのことを「同業者」と呼ぶことがあります。「今日は同業者が30人以上いた!」というように、現地の混雑状況を伝える言葉としても使われます。少しお茶目な言い回しが、撮り鉄さんたちのユーモアを感じさせますね。
- 駅撮(えきとり)/沿線撮り(えんせんどり):駅のホームで列車を撮るスタイルが「駅撮」、駅以外の場所(線路沿いの歩道橋や踏切付近など)で撮影するのが「沿線撮り」です。それぞれにメリットがあり、駅撮はアクセスがしやすく安全、沿線撮りは風景込みの写真が撮れるなど、好みに応じて選ばれます。
これらの言葉も、鉄道ファンならではの感覚が詰まっています。知っておくと、SNSの投稿を見たときや、実際の現地での会話ももっと楽しめるようになりますよ♪
まとめ|「テモる」は一体どんな言葉だったのか?

今回ご紹介した「テモる」は、鉄道ファンの間で生まれた、ちょっとユニークな表現でした。主に“トラブルや混乱”など、電車の運行に何らかの支障が出たときに使われることが多いこの言葉は、単なる迷惑行為というよりも、ファン同士が状況を軽く共有するための“ゆるい報告表現”のような役割も担っているようです。
とはいえ、その意味はまだまだ曖昧で、はっきりとした定義があるわけではありません。人によって使い方が少しずつ異なり、「またテモったっぽいね」「あのとき完全にテモってた」など、感覚的に使われている印象があります。でも、だからこそ広がりやすく、使っている人にとっては親しみのある言葉として自然と定着してきたのかもしれません。
鉄道ファンでない方にとっては、初めて聞くとちょっと不思議に思えるかもしれませんが、こうした言葉を知ることで、鉄道という趣味の世界がぐっと身近に感じられたり、新しい視点でSNSの投稿を楽しめるようになったりもします。
もし今後、SNSなどで「テモる」という言葉を目にしたら、「あっ、これってあの記事にあったやつだ!」とクスッと思い出してもらえたら嬉しいですし、鉄道に興味をもつきっかけのひとつになれたなら、もっと嬉しく思います。
言葉の背景や使い方を知ると、ただのスラングにも奥深さが感じられて面白いですよね。こうした知識を少しずつ集めていくことで、趣味の世界やネット文化への理解がどんどん広がっていくと思います。