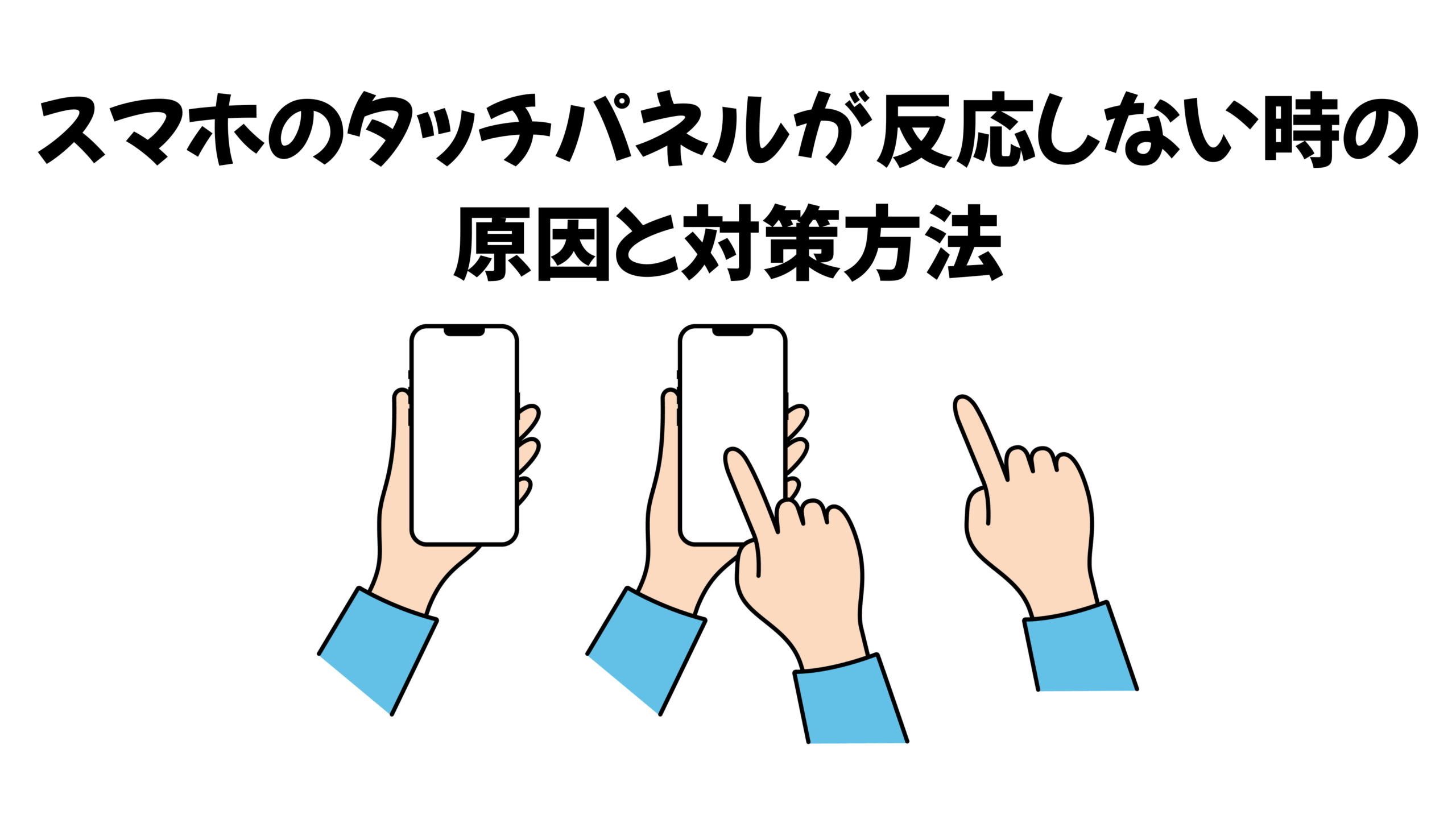スマートフォンのタッチパネルが突然反応しなくなった経験はありませんか?
現代のスマホはほとんどの操作を画面のタッチによって行うため、タッチパネルの不具合は非常に困る問題です。
画面の一部だけ反応しない、あるいは全く動かないといった症状は、軽度な設定ミスから深刻なハードウェアの故障まで、さまざまな原因が考えられます。
本記事では、「画面のタッチが反応しないときの対処法」をテーマに、主な原因とその確認方法、具体的な解決策について分かりやすく解説します。
iPhone・Androidなどの機種別対応や、冬場や手袋使用時の注意点、データ管理のポイントまで網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
スマホのタッチパネルが反応しない原因と対処法【全体解説】

反応しない症状の種類(一部・全く)
スマホのタッチパネルが反応しない症状には、大きく分けて「画面の一部だけ反応しない」ケースと、「全く反応しない」ケースの2種類があります。
部分的にタッチが効かない場合は、画面の汚れや指の乾燥、保護フィルムによる干渉、または特定アプリの不具合などが原因となることが多く見られます。
特に画面の端だけ反応しないなどの局所的な問題は、ソフトウェア的な誤作動か、画面保護アクセサリとの相性に起因していることがあります。
一方で、画面全体が完全に反応しない場合は、より深刻な原因が考えられます。
たとえば、OSのクラッシュ、端末のフリーズ、システムリソースの極端な消費、または水濡れ・落下などによるハードウェアの物理的な損傷が要因として挙げられます。
画面が真っ暗なまま操作不能になる場合や、電源は入っているがタッチに一切反応しない状態では、迅速な診断と適切な対処が重要です。
これらの症状を正しく見極めることで、最適な対応策を選びやすくなります。
タッチパネルが反応しない主な原因
主な原因としては、物理的な破損、静電気の発生、湿気や水濡れ、ソフトウェアの不具合、アプリの暴走、保護フィルムや画面保護ガラスの干渉、そしてストレージやメモリの容量不足などが挙げられます。
これらの原因は単体で起こることもあれば、複数が複雑に絡み合って発生する場合もあります。
たとえば、スマホを長時間使い続けた際に発生する熱や帯電が、内部回路やセンサーに影響を与えることで、タッチパネルの反応が鈍くなることがあります。
また、手汗や湿気により、静電容量方式のタッチセンサーが正常に動作しなくなるケースもあります。
特定のアプリを使用しているときだけタッチが効かない場合は、そのアプリ自体が原因である可能性が高く、削除やアップデートで改善されることがあります。
また、最近ではセキュリティ強化や視認性向上のために画面に厚手の保護フィルムや強化ガラスを貼るユーザーが増えていますが、これらがタッチ感度を低下させる要因となることも少なくありません。
さらに、写真や動画の保存によるストレージの逼迫が原因でシステムの処理速度が落ち、タッチ反応に遅延が生じるといった事例もあります。
このように、タッチパネルが反応しない背景にはさまざまな要因が考えられるため、症状の特徴を見極めつつ、順を追って一つひとつの原因を切り分けて対処することが大切です。
まず試したい基本の対処法STEP
- 画面を乾いた柔らかい布で拭く。
- タッチ不良の多くは、皮脂や汚れ、微細なホコリによる影響が原因となることがあります。クリーニングクロスやメガネ拭きのような柔らかい布で優しく拭き取りましょう。
- 保護フィルムを一時的に外す。
- 厚手のガラスフィルムや気泡・浮きのあるフィルムは感度を低下させる原因になります。一度フィルムを外し、素の画面で反応するかどうかを確認してください。
- スマホを再起動する。
- OSの軽微な不具合やアプリの一時的なバグは、再起動によって解消されることがあります。特に動作が重いと感じる場合は、電源を切って数十秒待ってから再起動するのが効果的です。
- アプリを強制終了またはアンインストール。
- 特定のアプリを使用中にのみタッチが反応しない場合、そのアプリが原因の可能性があります。アプリのキャッシュを削除したり、一度アンインストールして再インストールしてみると改善する場合があります。
- ストレージやメモリの空き容量を確認。
- ストレージがいっぱいになると、動作が遅くなるだけでなく、タッチ操作への反応も鈍くなる傾向があります。不要なアプリや画像・動画を整理し、2〜3GB程度の空きを確保しておくと安心です。
- タッチ感度設定の確認(機種により)
- 一部のAndroidスマホでは、「手袋モード」や「高感度モード」などの設定があり、それらをオンにすることで改善するケースもあります。設定メニューを確認してみましょう。
一部だけタッチが反応しない時の原因と解決方法
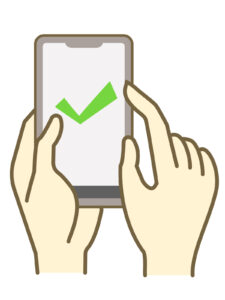
画面の汚れ・付着物による干渉
皮脂やホコリ、液体の飛沫が画面に付着していると、静電容量式のタッチパネルでは正しく反応しないことがあります。
特に、湿った指や食べ物の油分などが付着している場合、タッチの反応が極端に悪くなることがあります。
また、細かいゴミや砂ぼこりなどがセンサーの隙間に入り込むと、感度が不安定になることも。
スマホをポケットやバッグに入れたまま使っている人は、布くずや皮脂の蓄積が起きやすくなりますので、定期的に画面の清掃を行うことが大切です。
清掃にはアルコールフリーの専用クリーナーや、メガネ拭きなどのマイクロファイバークロスを使用し、優しく表面を拭き取りましょう。
乾いた布だけでなく、微量の水やクリーニング液を含ませた布を使うことで、指紋などもしっかりと除去できます。
また、画面保護フィルムの貼り付け面に微細なホコリが入り込んでいると、貼り方が綺麗でも干渉の原因になる場合があります。
そのようなときは、一度フィルムを剥がして再貼り付けするか、新しいものに交換するのが効果的です。
タッチパネルの精密さを保つためにも、日頃から画面の清潔さを保つ意識が大切です。
保護フィルムや画面保護シートの影響
保護フィルムの浮きや気泡、厚みが原因でタッチ感度が低下することがあります。
特に、安価なフィルムや非対応モデル用のフィルムを使用している場合、タッチパネルとの相性が悪く、操作時に反応しない、あるいは遅延が生じることがあります。
また、ガラス製のフィルムは耐久性に優れている反面、タッチ感度に悪影響を与えることもあり、フィルムの厚みや素材によっては細かい操作がしづらくなることもあります。
貼り付けの際に発生する気泡やホコリの混入も、部分的な感度低下の原因となるため、貼り付け作業には十分注意が必要です。
このような不具合がある場合は、まずフィルムを一時的に剥がして、素の画面での反応を確認してみましょう。
もし問題が解消するようであれば、フィルムの見直しが必要です。
高品質で端末対応済みのフィルムへ交換することで、快適な操作性を取り戻せる可能性があります。
また、定期的にフィルムの状態を確認し、劣化や浮きがあれば早めに交換することもおすすめです。
ソフトウェアやアプリの原因
特定アプリでのみ発生する場合、そのアプリの不具合の可能性があります。
たとえば、ゲームアプリやSNSアプリなどは、アップデート後のバグや互換性の問題でタッチの不具合を引き起こすことがあります。
このような場合は、アプリのキャッシュやデータを一度削除してみるか、最新版にアップデートを行うことで改善する可能性があります。
また、OS自体との相性問題も考えられるため、アプリの開発元が公開している不具合情報や対応状況を確認するのも有効です。
問題が続くようであれば、一時的にアプリをアンインストールし、別の代替アプリを使用することも検討しましょう。
さらに、バックグラウンドで多くのアプリが動作していると、システムのメモリを圧迫し、タッチパネルの反応が悪くなることがあります。
不要なアプリは定期的に終了させたり、不要なデータを整理することで、スマホ全体のパフォーマンス改善にもつながります。
タッチパネルが全く反応しない場合の対処法
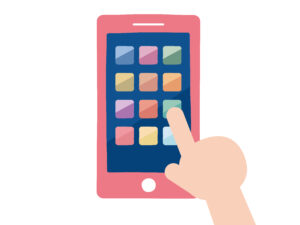
強制終了・再起動・リセットの方法
電源ボタンと音量ボタンの同時押しで強制再起動が可能です。
この操作は端末が完全にフリーズしてしまい、通常の方法でシャットダウンできない場合に特に有効です。
一般的には、電源ボタンと音量下ボタンを長押し(約10秒〜15秒)することで再起動が開始されますが、機種によっては音量上ボタンとの組み合わせが必要な場合もあります。
また、タッチ操作が効かない状況で画面が表示されている場合、端末によってはハードウェアリセット(ファクトリーリセット)を行う必要があります。
この手順は端末の初期化を伴い、すべてのデータが消去されるため、バックアップを取ってから実施することが推奨されます。
リセット方法は、リカバリーモードに入って物理ボタンで操作する形となり、操作方法はメーカーや機種ごとに異なります。
一部のスマートフォンでは、PCと接続して専用ソフトを使って再起動やシステム修復が可能な場合もあります。
たとえば、iPhoneであれば「Finder」や「iTunes」を使ったリカバリーモード、Android端末では「ADB(Android Debug Bridge)」を使った再起動指示が可能です。
このように、ただの電源オンオフでは解決しない場合は、機種に応じた方法を取る必要があるため、メーカーの公式サポートページや取扱説明書を確認しながら慎重に操作を進めてください。
フリーズやロック解除トラブルの対策
一時的なフリーズであれば、時間を置くことで自動的に復帰する場合があります。
たとえば、処理が一時的に重くなっているだけであれば、数分待つことで動作が再開されるケースも少なくありません。
その際は、スマートフォンの熱がこもっていないか、本体が異常に熱くなっていないかも確認してみてください。熱暴走によるフリーズの可能性もあります。
また、ロック解除時に指紋や顔認証が効かなくなるトラブルも報告されています。
これらはセンサーの汚れや湿気によって誤作動する場合があるため、センサー部分をきれいに拭いてから再試行すると改善することがあります。
それでも解除できない場合は、PINコードやパスコードでの手動解除を試みましょう。
もし時間を置いてもタッチがまったく反応しない、あるいはロック画面すら解除できない状態が続く場合は、次のステップとして端末の再起動やリセットを検討する必要があります。
これにより、メモリの開放や一時ファイルの解消によってシステムが正常な状態に戻る可能性があります。
どうしても復帰できない場合は、初期化の検討も必要ですが、まずはバックアップの有無を確認し、データ損失を最小限に抑えるよう注意しましょう。
電源オフ・本体乾燥・帯電トラブルの解決
湿気や水没後の反応不良には、まず速やかに電源を切って本体を乾燥させることが非常に重要です。
電源が入ったままの状態で水分が内部に侵入すると、ショートや基板の腐食を引き起こす可能性があります。
特に水没した場合は、電源を切るだけでなく、SIMカードやSDカードを抜き、できる限り端末内部を空気に触れさせて乾燥させるようにしましょう。
乾燥方法としては、風通しの良い場所での自然乾燥や、シリカゲル・乾燥剤と一緒にジップロックに入れて数日間放置する方法が効果的です。
ドライヤーの温風など高温で急速に乾かすのは、内部のパーツを痛める可能性があるため避けるべきです。
また、水に含まれる塩分や不純物が残っていると、その後もタッチパネルに不具合を起こす恐れがありますので、できれば防水スマホでない場合は専門の修理業者に相談するのが安心です。
一方、帯電による誤作動が原因と考えられる場合は、静電気を除去するために静電気防止マットや静電気除去シートを活用すると効果があります。
また、金属部分を素手で触れることで放電する方法や、電源をオフにして10分以上放置することで内部の帯電が解消されることもあります。
こうした対応を通じて、本来のタッチ操作の反応を回復できる場合が多いため、焦らず段階的に対処していきましょう。
iPhoneのタッチパネルが反応しない時の対処法

iOSアップデート・ソフトウェア問題の確認
iOSのバグや古いバージョンの影響でタッチ不良が起こることがあります。
特に、iOSのメジャーアップデート後には、ユーザーからタッチの遅延や一部エリアでの無反応といった不具合が報告されることも少なくありません。
Appleはこうしたバグに対して迅速にマイナーアップデートを配信することが多いため、常に最新の状態に保っておくことが重要です。
また、アップデート前後で不具合が出た場合は、一度端末を再起動してみたり、設定アプリ内の「一般」→「リセット」→「すべての設定をリセット」などを試すのも有効です。
これにより、個別アプリや設定による干渉を最小限に抑えることができます。
さらに、iOSベータ版を利用している場合は、安定性が低くなる傾向があるため、可能であれば正式版へ戻すことも検討してください。
iTunesまたはFinder経由での復元操作により、クリーンな状態へ戻すことで症状が改善されることもあります。
これらの操作を行う前には、念のためiCloudやiTunesを利用したバックアップを取っておくことをおすすめします。
アップデート作業中に不測の事態が発生しても、大切なデータを守ることができます。
保護フィルムやケースの干渉をチェック
特に端末の縁まで覆うケースやガラスフィルムが影響するケースがあります。
こうしたアクセサリーは、保護性能を高める一方で、タッチ操作の妨げとなることがあります。
特に、エッジ部分までカバーするタイプのフィルムや、厚みのあるガラス製フィルムは、画面端の反応が鈍くなる原因になります。
また、ケースが本体にぴったりと密着していない場合や、素材が硬すぎる場合は、端末のフレームを圧迫しタッチパネルに影響を与えることもあります。
加えて、ケースとフィルムの組み合わせによっては、タッチセンサーの動作に干渉しやすくなることもあるため注意が必要です。
一度ケースとフィルムを取り外し、素の状態でタッチ操作がスムーズかどうかを確認してみましょう。
改善が見られる場合は、より薄型でタッチ感度に配慮された設計の製品を選ぶか、端末に最適化された純正アクセサリーへの切り替えを検討するとよいでしょう。
こうした見直しを行うことで、不要な干渉を避け、快適な操作性を取り戻すことが可能です。
AppleCare・修理・修理費用の目安
保証期間内であれば、Apple StoreやApple正規サービスプロバイダ(AASP)に相談するのが最も安全で確実な方法です。
AppleCare+に加入している場合は、自己負担金が大幅に軽減され、画面修理などが比較的安価に行えます。
修理の際には、事前にApple公式サイトやAppleサポートアプリで予約を取ると、スムーズに対応してもらえます。
来店が難しい場合は、宅配修理サービスを利用することも可能です。
また、軽微な不具合であれば、正規店での診断だけで済むケースもあり、その場合は無料でアドバイスを受けられることもあります。
修理費用は使用している機種や破損の状態により異なり、ディスプレイ交換のほか、筐体全体の交換となるケースもあります。特に水没や落下による深刻なダメージがある場合、修理では対応できず、本体交換が案内されることもあるため、事前に見積もりを確認することが重要です。
Appleの公式ページでは、モデル別の料金表が公開されており、事前に目安として確認しておくと安心です。
Androidスマホでタッチパネルが反応しない時の解説
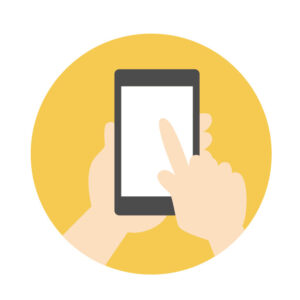
Android特有のモード・操作ミスの確認
「開発者向けオプション」や「誤操作防止モード」が有効になっていると反応しにくくなる場合があります。
たとえば、「誤操作防止モード」はポケットの中や通話中の誤タッチを防止するための機能であり、画面の一部や特定の動作が無効化されていることがあります。
このモードがオンになっていると、手の一部で画面を触れただけでは認識しなかったり、操作範囲が制限される場合があります。
「開発者向けオプション」では、タッチ表示のオーバーレイやアニメーションスケール設定などが影響を与えることもあります。
これらの設定を変更した覚えがある場合、元に戻してみることで症状が改善することがあります。
また、ジェスチャーナビゲーションの操作方法やスクリーンショットの撮影動作など、特定の動作がタッチの誤動作につながるケースもあるため、設定メニューを一度見直してみましょう。
さらに、Androidの一部機種では「感圧モード」や「片手モード」「キッズモード」など特殊な操作モードが搭載されており、これらが意図せずオンになっていることでタッチの動作に違和感を感じることがあります。
特にソフトウェアアップデート後などは、初期設定にリセットされたり、自動的に一部の機能が有効になる場合もあるため注意が必要です。
こうしたモードは設定アプリ内の「ディスプレイ」「ジェスチャー」「システム」などの項目から確認・変更が可能ですので、不具合が生じた場合にはまず設定項目を一つひとつチェックして、不要なモードをオフにすることで改善を図ることが推奨されます。
アプリやキャッシュの削除とストレージ容量不足対策
一部アプリのキャッシュが悪さをしている場合があります。
設定アプリからキャッシュ削除や不要アプリの整理を行いましょう。
特にSNSや動画アプリ、ゲームアプリなどは短期間で大量のキャッシュデータを生成する傾向があり、これがシステムリソースを圧迫してタッチパネルの挙動に影響を及ぼすことがあります。
キャッシュの削除は、Android端末では「設定」→「アプリ」→対象アプリの「ストレージ」から実施できます。
iPhoneではアプリの再インストールが必要なケースもあります。
また、使用していないアプリは思い切ってアンインストールすることで、ストレージの空き容量を増やし、動作全体のパフォーマンス改善にもつながります。
加えて、写真や動画、ダウンロードファイルなどの不要データを定期的に整理することも重要です。
クラウドサービスを活用してデータを移動させるか、SDカードへ保存して内部ストレージの負担を軽減しましょう。
ストレージの空き容量が不足していると、OSが正常に動作せず、タッチ操作に遅延が発生する原因にもなるため、常に1〜2GB以上の空きを保つよう心がけると良いでしょう。
タッチパネルの感度が悪い・冬場や手袋を使う時の対処法

静電気や乾燥・保湿が必要なケース
空気が乾燥する冬場は静電気の影響でタッチパネルの感度が落ちることがあります。
特に静電容量方式のパネルを採用しているスマートフォンでは、皮膚と画面との間で発生する微細な電流が感知の基本であるため、手が乾燥していると反応しづらくなる傾向があります。
そのため、手指の保湿は非常に重要です。
外出前やスマートフォンを使う前に保湿クリームやハンドローションを軽く塗るだけでも、指先の導電性が改善され、タッチの反応が良くなることがあります。
また、室内では加湿器を使用して湿度を40〜60%に保つことで、乾燥を防ぎ静電気の発生も抑えられます。
加えて、冬場に多く発生する「パチッ」とした放電のような静電気は、スマートフォン本体にも影響を及ぼす可能性があり、誤作動や一時的なセンサーの誤反応を引き起こす場合があります。
このような帯電対策としては、導電性の高い素材の手袋を使ったり、静電気除去シートをポケットに入れるといった方法も効果的です。
特に冷えた環境では画面の反応も鈍くなるため、端末をポケットなどで暖めておくのもひとつの方法です。
こうした工夫を組み合わせることで、冬場でもスムーズなタッチ操作を維持しやすくなります。
感度調整や設定変更の具体的方法
機種によっては感度設定が可能です。
「手袋モード」や「感度強化設定」をONにしてみましょう。
特に寒い季節や屋外で手袋を着用する場面では、感度が下がることでタッチ操作が効かなくなることがあります。
そのため、多くのスマートフォンでは「手袋モード」や「高感度モード」といった設定が用意されています。
これらを有効にすることで、通常よりも微弱な電気信号でも反応しやすくなり、操作性が改善される可能性があります。
設定の場所は機種により異なりますが、一般的には「設定」アプリ内の「ディスプレイ」や「高度な設定」「タッチ操作」などの項目からアクセス可能です。
また、一部機種では専用のアプリやウィジェットを介して感度調整が行える場合もあります。
加えて、画面の保護フィルムが厚い場合や、ガラス製フィルムを使用していると、タッチの感度が下がることがあります。
感度調整とあわせて、フィルムの材質や貼り付け状態も見直すとよいでしょう。
最新の機種では自動的に感度を調整してくれる機能もありますので、取扱説明書や公式サポート情報を参考にしながら、自分の使用環境に最適な設定を見つけることが重要です。
手袋・保護シートなどアクセサリとの干渉対策
手袋対応モデル以外では、薄手の導電性手袋を使用するか、保護シートの見直しを検討します。
特に通常のウールや綿素材の手袋では、スマホの静電容量方式タッチパネルが反応しないことがほとんどです。
導電性素材を使用した手袋であれば、指先から微弱な電流を通すことができ、画面操作が可能になります。
近年ではファッション性と機能性を両立した導電性手袋も数多く登場しており、寒い冬でも快適にスマホを使用できる選択肢が広がっています。
一方で、保護シートの厚みや素材によっても、タッチ感度に影響が出る場合があります。
特に硬度の高いガラスフィルムや、エッジまで覆う3Dフィルムなどは、感度を低下させる可能性があります。
こうした場合には、感度向上機能付きのフィルムに交換することや、保護シートを貼り直して気泡を取り除くなどの工夫が必要です。
さらに、ケースとの組み合わせによって、タッチパネルの反応が悪化することもあるため、アクセサリを一時的にすべて取り外し、素の状態で操作性を確認するのも有効です。
その結果、改善が見られる場合は、アクセサリの変更や見直しを検討しましょう。
データや設定の管理とバックアップ手順

バックアップ・データ消去・初期化の方法
GoogleアカウントやiCloudでの自動バックアップを活用し、問題が解消しない場合は初期化も選択肢になります。
自動バックアップ機能は、スマホの設定メニューから簡単にオンにすることができ、写真や連絡先、アプリのデータなどがクラウド上に定期的に保存される仕組みです。
これにより、端末に不具合が発生した場合でも、別の端末でデータを復元することが可能になります。
さらに、重要なデータは手動でのバックアップも推奨されます。
たとえば、GoogleフォトやiCloud Driveに加えて、パソコンへのファイルコピーや外部ストレージ(USBメモリやSDカード)への保存も併用することで、万が一の故障やデータ消失に備えることができます。
スマートフォンを初期化する場合は、必ず事前にすべてのバックアップを完了させてから実行しましょう。
初期化は「設定」→「システム」→「リセット」→「すべてのデータを消去(出荷時設定にリセット)」といった手順で行えますが、操作方法はOSや機種によって異なるため、あらかじめ確認が必要です。
また、アカウント情報やサインイン情報も控えておくと、初期化後の再設定がスムーズに行えます。
アプリ・履歴・キャッシュのクリア手順
不要アプリやキャッシュデータを削除することで、不具合の解消や動作改善が見込めます。
特にSNSアプリやニュースアプリ、動画視聴アプリなどはバックグラウンドで多くのデータを蓄積する傾向があり、これがスマートフォンの動作を重くし、タッチ反応にも影響を与えることがあります。
Androidでは、「設定」→「アプリ」→「ストレージ」から、各アプリごとのキャッシュデータを削除することができます。
iPhoneでは、アプリを一度削除して再インストールすることで、キャッシュを一掃する方法が一般的です。
また、ブラウザアプリなどでは「閲覧履歴」や「Cookie」「サイトデータ」も蓄積されやすいため、定期的に削除することでパフォーマンス向上が期待できます。
履歴の整理も重要です。
電話アプリの通話履歴や、メッセージアプリの過去ログ、検索履歴なども端末の記憶領域を占める要因のひとつです。
使用頻度が低いアプリの履歴は削除しておくと、タッチ操作時のレスポンス向上にもつながります。
さらに、定期的にメモリクリーナーアプリを使用したり、マルチタスク画面から不要なアプリを終了させることで、端末の負荷を軽減できます。
これらの手順を組み合わせることで、スマホ全体の安定性が向上し、タッチパネルの反応改善にもつながります。
ストレージ容量の定期的な確認とメモリ管理
定期的に写真や動画の整理、不要ファイルの削除を行うことがスマホの健康維持につながります。特に写真や動画はファイルサイズが大きいため、知らぬ間にストレージを圧迫していることが少なくありません。
撮影後すぐにクラウドに保存したり、SDカードなどの外部ストレージに移動する習慣をつけると、スマホ本体の容量を節約できます。
また、アプリが生成する一時ファイルやダウンロードフォルダの不要データも見落としがちです。定期的に「ファイル」アプリなどを使って端末全体のストレージ構成をチェックし、大容量を占めているファイルを見つけ出すことが重要です。
特にアプリによってはキャッシュとは別に「データフォルダ」にログやメディアデータを保管している場合もあります。
さらに、メモリ(RAM)の最適化も忘れてはいけません。
複数のアプリを同時に開いたままにしていると、メモリが逼迫し、端末の処理能力が低下してタッチの反応にも影響が出ます。
マルチタスク画面で使用していないアプリを閉じたり、不要なバックグラウンドアプリを制限することで、スマホの動作をスムーズに保つことができます。
このように、ストレージとメモリの管理は日常的なスマホメンテナンスの一環として習慣化することが望ましく、長期的に安定したパフォーマンスを維持するためのカギとなります。
まとめ

スマホのタッチパネルが反応しない原因は多岐にわたり、ソフトウェアの不具合から物理的な損傷、設定ミス、アクセサリの干渉まで幅広く存在します。
まずは簡単な掃除や再起動から始め、段階的に原因を切り分けていくことで、多くのトラブルは自力で解消できます。
iPhoneやAndroidなどのOSごとの対処法、冬場の静電気対策、アプリやストレージ管理の重要性、さらには修理や機種変更を検討すべきタイミングなども意識しておくことが大切です。
特にデータのバックアップや設定の保存は、万が一の際にも安心できる備えとなります。
タッチパネルの不調はストレスの原因にもなり得ますが、適切な知識を持っていれば、慌てず冷静に対応することができます。
今後同様の不具合が発生した際にも、本記事の内容を活用して、スムーズに問題を解決していただければ幸いです。